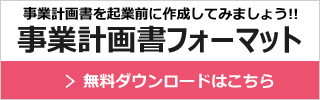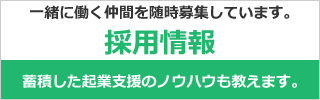事業目的における制作と製作の使い分け
会社設立の際に必ず決めなければならないのが事業目的です。今では具体性がなくても会社設立登記には支障がなくなったとはいえ、せっかく設立する会社なので事業目的にもある程度はこだわりたいという人も多いと思います。
今回は、事業目的の中でも頻出の言葉「製作」と「制作」の違いについて考えてみます。
辞書で引いてみると、
制作-芸術作品などを作ること。
製作-道具や機械などを使って品物を作ること。
といったことが一つ目の意味として記載されています。どちらも作ることということで、よく区別が分からないので、具体的な事例を挙げて考えてみましょう。
「ホームページの制作」と「ホームページの製作」という言い方ではどのように異なるのでしょうか?
イメージとしては制作は全体を作り上げること、製作は具体的な作業を指す感じです。ホームページについてお客様に納品するまでの工程を管理して完成までもっていくということは「制作」にあたります。一方、ホームページの一部の機能や画像、デザインなど個別のプロセスについは「製作」という言葉が適切と区分できます。
この例はホームページというソフト的なもので例を挙げましたが、モノ、つまりハード的なものでも同じイメージで使えます。
「実用品の制作」といえばその商品の機能やデザインなどを決めて商品化できるように持っていくこと、「実用品の製作」といえば実際に製造する行為を指します。
このような区分で考えていくと、会社設立の場合の事業目的に使うのは「制作」が多いように思えます。一人で会社を設立して製造までを一貫して行うことは少なく、商品のコンセプトを決めてあとは外注先やOEM先に発注という流れであれば「制作」です。ただ、職人的なこだわりを持った商品を自社で製造するのであれば、あえて「製作」という言葉を使うのもよいかもしれません。
このように、言葉にもこだわりを持って事業目的を考えてみるのも会社設立のプロセスの楽しみの一つといえるかもしれません。
この記事の執筆者

-
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
最新の投稿
 会社法2024年10月29日疑似外国会社とは
会社法2024年10月29日疑似外国会社とは 会社法2024年10月27日合同会社の社員の入退社に伴う定款の書き換え、変更は必要?
会社法2024年10月27日合同会社の社員の入退社に伴う定款の書き換え、変更は必要? 会社法2024年10月25日持分の払戻しが発生する場合の合同会社の社員の退社の効力発生日
会社法2024年10月25日持分の払戻しが発生する場合の合同会社の社員の退社の効力発生日 会社法2024年10月23日会社設立の際の1株当たりの単価はいくらにすべき?
会社法2024年10月23日会社設立の際の1株当たりの単価はいくらにすべき?