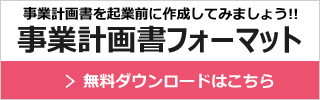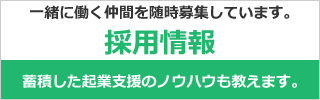会社設立時には、事業目的を決めて定款に記載するとともに、登記が必要になります。飲食店であれば、「飲食店の経営」など、行う事業を記載します。
会社設立時には、事業目的を決めて定款に記載するとともに、登記が必要になります。飲食店であれば、「飲食店の経営」など、行う事業を記載します。
それでは、事業目的として登記したもの以外のビジネスを行った場合どうなるのでしょうか?
ちょっと難しい言い回しですが、民法上は法人の権利能力は定款などで定められた目的の範囲に限られる、つまり、事業目的として登記したことの範囲内でのみ権利や義務の主体となれるとなっています。
では、たとえば、飲食店の経営としか登記されていない会社が雑貨の小売りを始めた場合どうなるのでしょうか?もちろん、小売業が事業目的として登記されていないからといってこの店で買ってはいけない、なんて考えるお客様はいませんよね。法律上、事業目的に書いていないことをやったからといって処罰するなんて条文はありません。(もちろんそれ自体犯罪に該当する場合は別ですが。)税務署も、しっかり小売業の利益も申告していれば事業目的に書いていないことで売上を上げているからといって文句はいいません。
事業目的に書いていないビジネスを行ったことで一番困る人は誰でしょうか?それは、その事業によって損を被ってしまった人です。では、その人が事業目的に書いていないビジネスだから取引は無効だといった訴えを起こした場合。これも裁判所が事業目的に書いてないから無効といった判決を出すことは皆無でしょう。過去の判例でも、「目的の範囲内の行為とは、定款(つまり登記)に明示された目的自体ではなく、その目的を遂行する上で直接的または間接的に必要な行為を全て含む。」といっています。当事者がいったん合意したことを事業目的を理由に無効にするのは、取引の安全性を損ねてしまいます。
このように、事業目的に書いていないビジネスを行ったからといって、即違法となるわけではありませんし、その会社に何らかの不利益が出るケースはまれでしょう。小さな会社だと、ちょっと新規事業を開始しようとするだけでいちいち事業目的を追加していてはコストがかかってしまいます。
ただし、取引先によっては、取引開始にあたって登記の内容を調査する場合があります。そこに事業目的として、取引するビジネスが記載されていなければ、事業目的を追加するなどの対応が必要かもしれませんし、投資を集める場合でも事業目的はしっかりと整備しておいた方がよいでしょう。